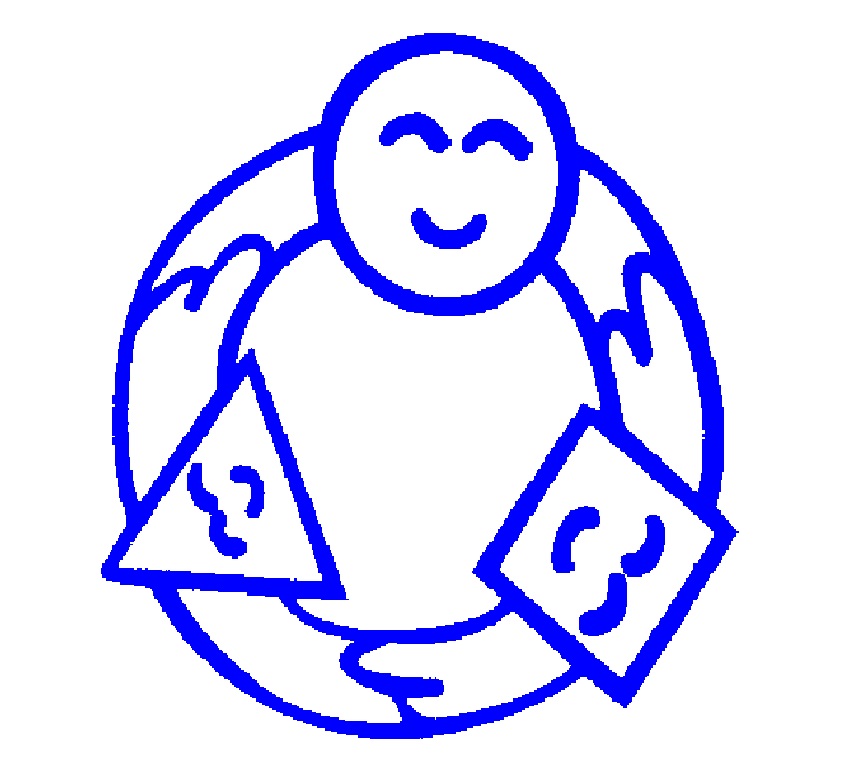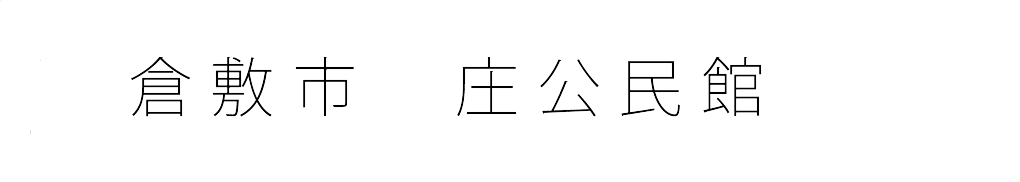研修活動
令和7年度 手話教室・手話交流会
 |
 |
|
7月19日(土)、庄手話サークルの皆様にご協力いただき、聴覚障がいに対する理解と認識を深めていただく目的で、手話教室・手話交流会を行いました。 毎回、子どもも大人も手話に興味が持てるように、サークルの皆様が工夫を凝らした内容を考えてくださります。当日は、庄小・中学校の児童生徒、保護者の皆様、教職員の方、地域の方々など約38名の皆様にご参加いただきました。 |
|
令和7年度 研修視察
9/6(土) 岡山市人権啓発センター・渋染一揆資料館
|
||||||